みなさん、こんにちは。
忙しいから 楽しいに。~ 未来が見える(だから)笑顔になれる ~
皆様の成長促進パートナー
中小企業診断士のまっちゃんです。
中小企業の現場を駆け回り、組織改革や事業承継などの課題解決をお手伝いしています。そして補助金申請支援などを通じた経営力強化のサポートもしています。
最近、ニュースやセミナーで「生成AI」という言葉を聞かない日はないのではないでしょうか。生成AIの進化は目覚ましく、新しい生成AIも登場しています。文章作成、アイデア出し、情報収集などなど、その能力の高さには目を見張るものがあります。「これは経営にも使えるのでは?」と、期待を寄せている経営者の方も多いのではないでしょうか。
特に、多くの時間と労力を要するものといえば、例えば、「経営計画」の策定ではないでしょうか。市場調査、自社分析、戦略立案、数値計画など。「これをAIが手伝ってくれたら、どれだけ楽になるだろう…。」そんな声も聞こえてきそうです。ニーズが高い補助金申請などは、多くは計画書作成が必須となっているので、なおさらです。そこで、今回は生成AIは、経営計画の策定に貢献できるのかをテーマに考えてみたいと思います。
このブログ記事を読むと、
経営計画を立てるのって、正直しんどい…。でも、AIが助けてくれるかもしれません。
最近よく耳にする「生成AI」。文章作成や情報整理のスピードに驚いた方も多いのではないでしょうか。では、このAIを経営計画づくりに使ったらどうなる?
本記事では、AIの力を活かしつつ、経営計画の本質である“人間の意志”をどう守り抜くかをテーマに、活用のヒントや注意点をお伝えします。経営者としての“想い”をカタチにしたい方に、きっとヒントになるはずです。
をお伝えします。
目次
- 経営計画とは「未来を創る意志」そのもの
- 生成AIでできること・できないこと
- 「もっともらしさ」の罠・AI活用3つのリスク
- AI時代にこそ輝く「人間力」
- 生成AIは“伴走者”。経営者が舵を取る時代へ
- AIと共に、自社の「未来の景色」を描こう
では、本題です。「生成AIは、経営計画の策定に本当に貢献できるのか?」
経営計画とは「未来を創る意志」そのもの
結論から申し上げると、私の答えは、「使い方次第で、強力な『考える道具』にはなり得る。しかし、決して計画策定の『主体』にはなれないし、なってはいけない」です。
そもそも経営計画とは何でしょうか?単なる目標数値や行動リストが書かれた書類ではありません。それは、「自分たちの会社を、将来どうしたいのか」という経営者の、そして社員一人ひとりの「意志」と「願い」を結晶させ、未来への道筋を描く、極めて人間的な営みだと思います。
これまで、多くの計画策定支援の経験から、最も大切にしているのは、この「意志」の確認です。まず最初に経営者の方にお伺いするのは、「この事業を通じて、社会や顧客にどんな価値を提供したいですか?」「5年後、10年後、社員がどんな顔で働いている会社になっていたいですか?」ということです。現場で単刀直入に話を切り出したりしません。。
これは、①経営理念やビジョン、「どうありたいか」という会社の魂、根っこの部分になります。
ここが揺らぐと、どんなに精緻な計画も砂上の楼閣になりがち。今は良くても持続的な成長は見込みにくいです。「ありたい姿」が明確になって初めて、
①経営理念やビジョン、「どうありたいか」の続き、
②現状とありたい姿とのギャップ(課題)は何か?
③そのギャップを埋めるための解決策(戦略)は何か?
④解決策を実行するための具体的な行動(戦術)は何か?
⑤行動の結果、どのような効果(成果)が期待できるか?
という具体的なステップが始まります。

生成AIでできること・できないこと
では、生成AIはこの人間的なプロセスにどう貢献できるのでしょうか?
現在の生成AIは、情報収集・整理、文章作成、アイデア発想支援など、特定のタスクにおいては驚異的な効率化をもたらします。特に、②の現状分析における市場データや競合情報の要約、③④⑤の戦略・戦術の選択肢提示や文章ドラフト作成など、「作業」レベルでは大きな力を発揮する可能性を感じています。
最近、「生成AIである補助金の申請マニュアルができないだろうか?」という興味が強く湧いてきて、、AIにマニュアル作成を指示してみました。提供した資料や意図を汲み取り、AIは詳細で実践的なマニュアル案を生成してくれました。ダミーの経営計画書も素晴らしいものです。AIの情報処理能力と文章構成能力の高さに感嘆しました。
しかし、あくまで私の「問い」に対するAIが導き出した応答であり、それ自体が特定の事業者の血肉となった経営計画ではありません。
「もっともらしさ」の罠・AI活用3つのリスク
生成AIが提示する回答は、時に非常に「もっともらしい」ものだと思います。私もAIの回答に、おーっ、思うことも多いです。でも、注意も必要です。例えば、次のようなことが考えられると思います。
3つのリスク
①情報の偏り(バイアス)
②情報の正確性と鮮度
③情報セキュリティリスク
AIの学習データは、ネット上にあるものや、意図的に学習させたものですから偏っている可能性がありますし、AIの情報は必ずしも最新・正確とは限りません。また、安易に会社の機密情報や個人情報を入力すれば、情報が漏洩のリスクも考えられます。やはり、いくら優秀でもAI任せにせず、最後は人の判断が求められると感じます。
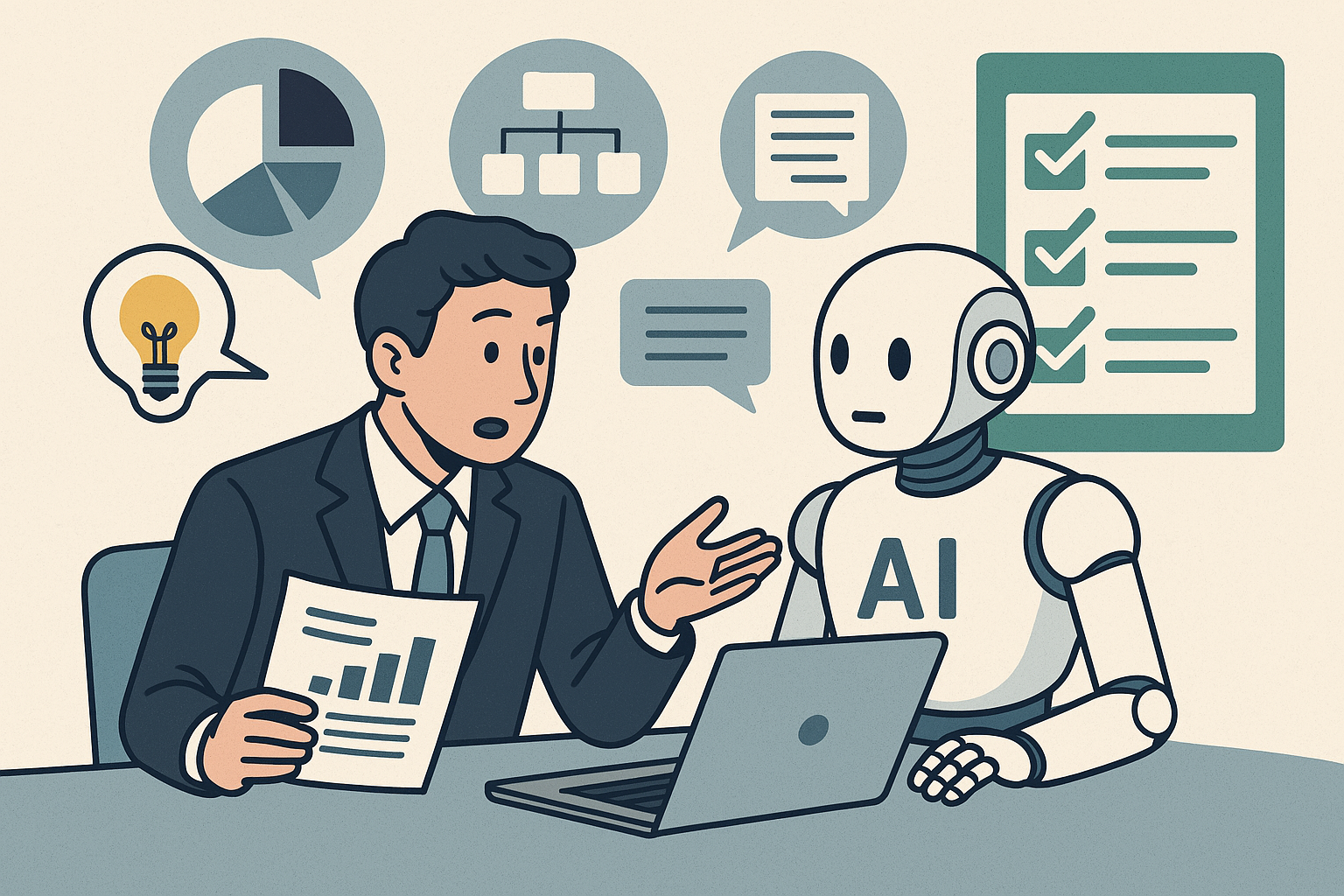
AI時代にこそ輝く「人間力」
AIには、無限の可能性を感じるものの、不得手なこともあります。それは、『感情と責任』だと思っています。なので、逆説的ですが、AIが進化すればするほど、人間にしかできないことの価値もますます高まるように感じます。例えば、人間ならではの価値は事業の根幹となる①「問いを立てる力」から始まり、次に②「共感し、巻き込む力」。ビジョンを実現するためには、多様な価値観を持つ人々の感情を理解し、対話を通じて心を一つにして目標に向かって進む必要があるからです。さらに、それを形にする③「創造性」も求められる場面も多々あります。加えて、覚悟を持って意思決定を下す④「倫理観と決断力」も試されます。これら全てのプロセスと、その決断の結果に対して、最後まで責任を持つ姿勢が人間ならではの価値ある営みなのだと思います。
生成AIは“伴走者”。経営者が舵を取る時代へ
ここまで持論を含めお伝えしました。どうでしょう?これからも人間中心のプロセスなら、生成AIは計画策定の強力な「ツール」、あるいは「伴走者」となり得ると思いませんか?
生成AI活用のオススメを3つ挙げてみたいと思います。
①思考の壁打ち相手になってもらう
②情報収集や整理の効率化を手伝ってもらう
③文章作成のアシスタントになってもらう
どうでしょうか?あくまで「経営者の意志を実現するための道具」として、私たちが主体的に活用すると、AIは人間(経営者と社員)と良きパートナーになりそうな気がしませんか。
AIと共に、自社の「未来の景色」を描こう
特に、私たち中小企業は、限られた経営資源を最大限に活用する必要があると思います。これから、AIを使ってみたいと考えていましたら、「流行っているから導入する」のではなく、「自社にとって、AIは有効な手段か?」という視点で、例えば無料ツールで試したり、特定の業務に限定して導入するなど、身の丈に合ったスモールスタートで、AIとの付き合い方を学んでいってはどうでしょうか。AIに詳しい外部専門家にも相談するのもよいと思います。
みなさんの会社は、5年後、10年後、どんな景色を見ていたいですか?
まずは時間を取って、その「ありたい姿」を言葉にしてみませんか? そして、その実現のために、AIはどのような「お手伝い」ができそうでしょうか? ぜひ、社内で熱く語り合ってみてください。
生成AIの進化は目覚ましく、このブログ記事を書いているときから、この記事も鮮度が下がっています。ぜひ、みなさんの貴重な経験や感想などをフィードバックしてもらえると嬉しいです。
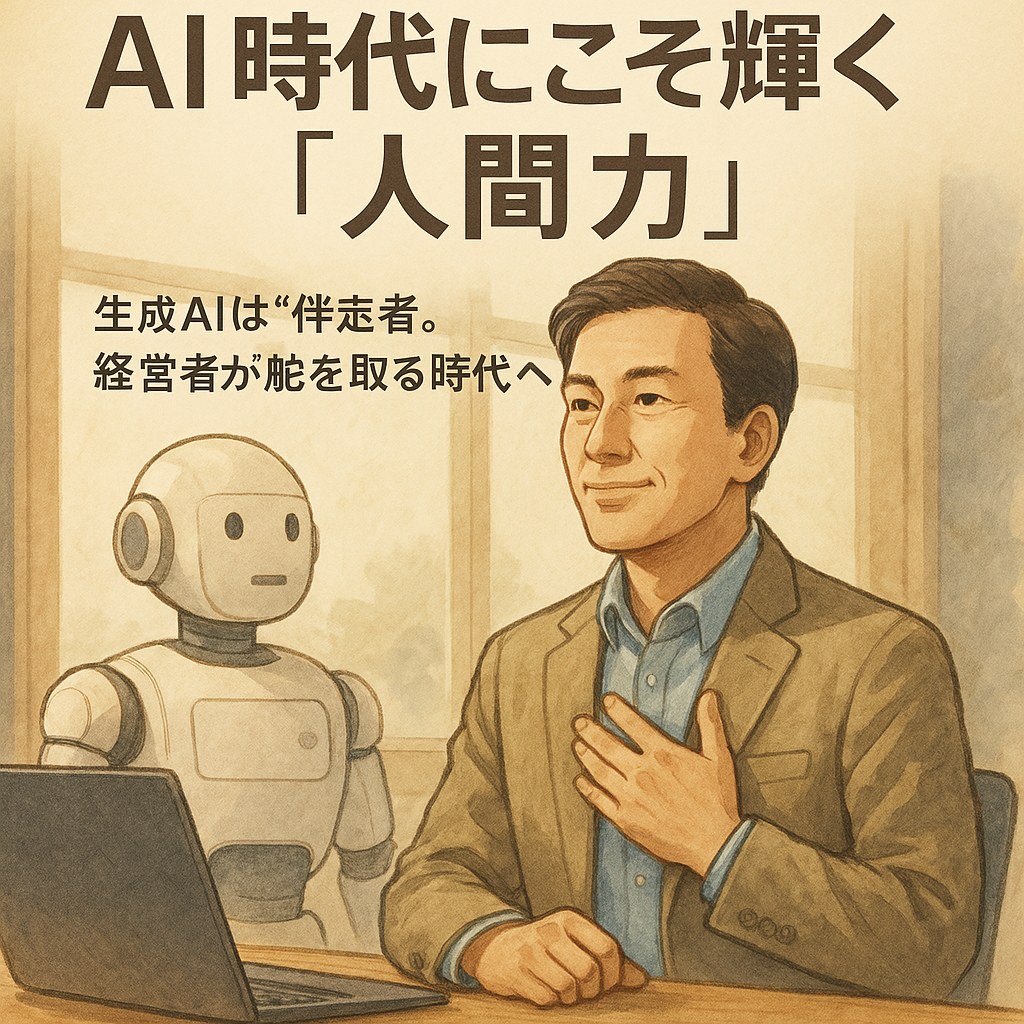
今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。
みなさんのご助言、情報提供などは、こちらから
こちらのサイト(note)からもご覧いただけます。












この記事へのコメントはありません。